
| トップページ | |
| 記念館への期待 | |
| 雪嶺プロフィール | |
| 展示案内 | |
| ● その時代と人生 | |
| ● 師・友・ライバル | |
| ● 雪嶺のいる風景 | |
| 主な収蔵品 | |
| ご利用案内 | |
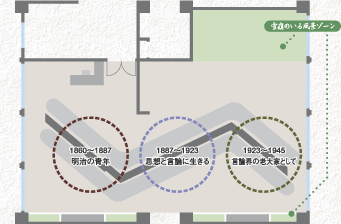 |
|
雪嶺は、欧米の学者・芸術家・思想家などが、自分の家を小さな図書館のようにして、所蔵しているものを展示公開しているのを実地に見聞して、いずれは自分もそのような小図書館を造りたいと考えていた。建築家になった長男勤はゆくゆくは私が設計して造ってあげましょうといって父親を喜ばせていた。 その勤が東京市技師として日本橋区役所の震災復興事業を監督中、建築機材の落下により殉職した。妻・美代子は結婚二年、息子は生後五ヶ月の別離であった。雪嶺の悲しみは深く、喜怒哀楽を滅多にあらわさない彼が、数日後に大声をあげて泣いたという。 工事を担当した鴻池組は、責任を感じて雪嶺のために小図書館を建設することとした。その小図書館が三宅文庫であり、書斎と居間を兼ね備えていた。昭和初期の特徴を色濃くあらわすこの建物は、勤の親友で、のちに早稲田大学名誉教授となった今井兼次の設計になる。昭和五年四月十九日に開庫の披露をし、よく雪嶺邸を訪れる人が百二十人ほど集まったという。 その文庫で、週に何回かの口述筆記が行われた。筆記者用のテーブルには本立てがあり、国語辞典・年鑑などが配置されていた。部屋の中央には来客用の椅子やテーブルが置かれ、壁際には愛蔵書の書棚があった。隣りの小部屋には昼寝用のベッドがあった。 口述筆記は、戦時中は長男の妻・美代子が行った。「難解な自分の文章を筆記できるか」と思ったが、誤字もなく安心した、と彼女を褒めた。また『婦人之友』の筆記には、同社の名記者・千葉貞子があたった。戦後最晩年の筆記者は、軍隊から復員した中野正剛の四男・泰雄であった。隔日に寄稿する新聞の原稿や書評、依頼された序文などは柔らかい鉛筆で自分で書いた。 |
 完成当時の三宅文庫。 文庫は昭和5年に完成した。  三宅文庫二階のようす |
Copyright (C) 1999-2007 Ryutsu Keizai University All Rights Reserved.